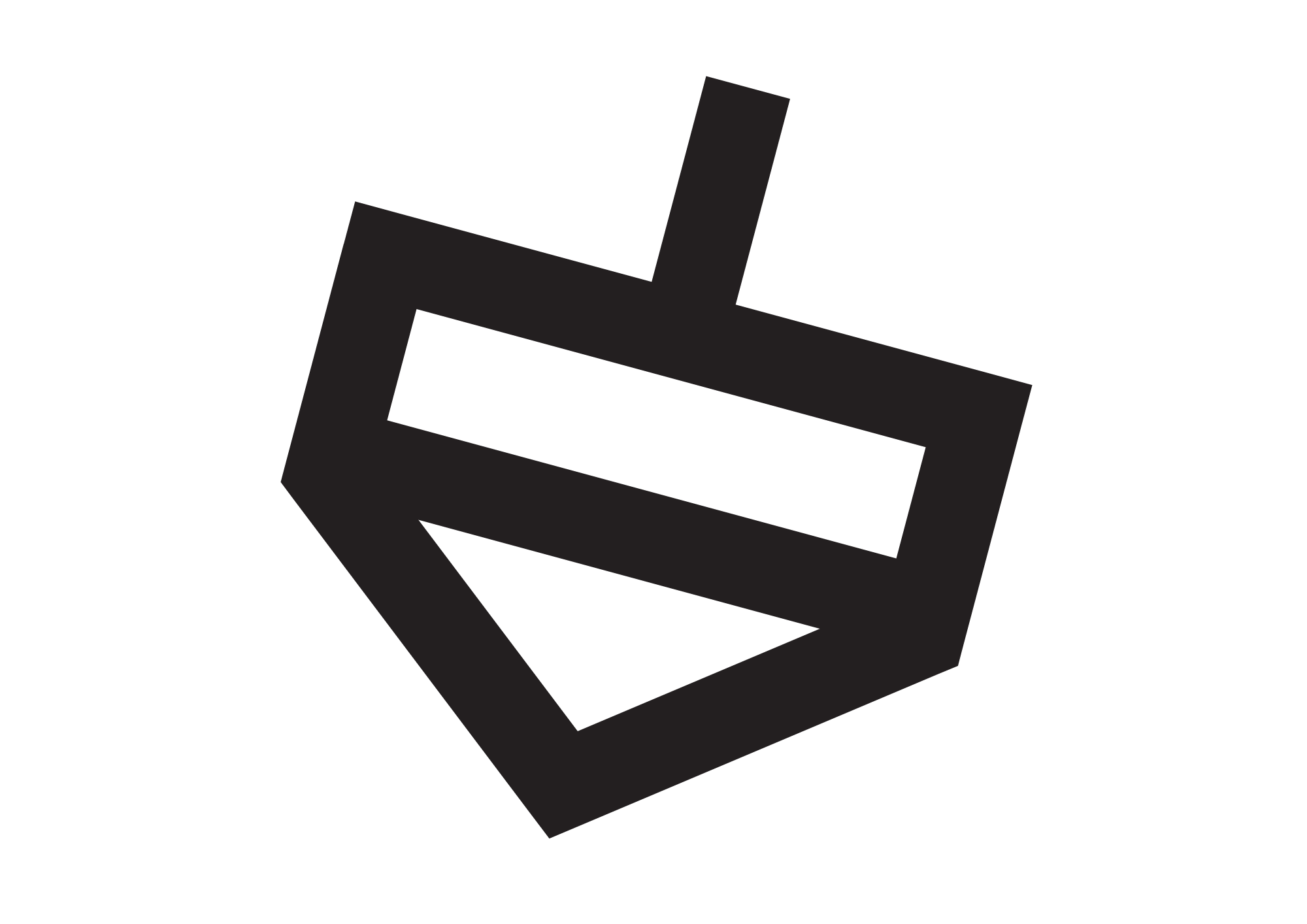最初の仕事
ここに書くのは、私自身のこれまでの仕事の歩みと、workspace comaをつくろうと思った理由です。
少し長いですが、読んでいただけたら嬉しいです。
会計事務所に勤めていた頃、私が一番楽しみにしていたのは、経営者と話す時間でした。
決算や試算表をもとに数字を振り返っていくと、その会社でどんな出来事があったのかが自然と見えてきます。
「この月は新しい取引を始めたんだ」
「ここで少し売上が落ちたのは、あの時期の影響だった」
数字は冷たいもののように見えて、実はストーリーを持っている。
そして、その振り返りが終わると、経営者は必ず未来のことを話してくれました。
「次はこうしたい」
「こんなサービスに挑戦してみたい」
まだ数字に現れていないけれど、これから形になっていくもの。
その声を聞く時間が、私にとって一番の楽しみでした。
数字だけを扱っているときよりも、人の声だけを聞いているときよりも、
両方を行き来することで、会社が前に進んでいく力を強く感じられる。
その瞬間に立ち会えることが、何よりのやりがいだったのです。
次の仕事
会計事務所を経て、私はベンチャー企業に入りました。
そこでは「外から数字を見る顧問」ではなく、経理担当者として組織の中から会社を支える立場になりました。
日々の入出金管理や請求書の処理、月末の支払い調整。
資金繰りに悩み、時には緊張感を持って銀行とやり取りをする。
数字が会社の息づかいそのものと直結しているのを感じました。
特に印象に残っているのは、組織の一員として動いた感覚です。
経営陣の判断はトップダウンで降りてくることもあります。
でも、その中で私はボトムアップとして支える役割を担っていました。
細かい数字を整え、現場を回すことで会社を前に進める。
その積み重ねが、自分のサービスを後に「丁寧に届ける」感覚につながっていると思います。
独立
会計事務所の外から、ベンチャー企業の中から──その次に選んだのは独立でした。
フリーランスとして経理サービスを請け負い、週に数日だけ出社して仕事をする。
時間の自由さはそれほどなかったけれど、選択の自由さがある。
どんな案件を受け、どのように進めるかを自分で決められる。
その裁量がとても楽しく、自分のスタイルに合っていると感じました。
経理サービスは少しずつ形になり、今の取引先と長く付き合っていきたいと思えるようになりました。
安定が見え始めたからこそ、「この先、自分はどう成長していくのか」と考えるようになったのです。
新しい試み
新しい挑戦を考えたときに浮かんだのは、自分自身の小さな事業を持ちたいという気持ちでした。
バックオフィスの仕事は、どうしても従業員の延長のような感覚が残ります。
だからこそ、自分の拠点を持つなら、その場所は地元がふさわしいと考えました。
外では、大きな数字やスピード感のあるプロジェクトに関わる。
一方で、地元では小さな事業を持つ。
外と内の両方に軸を置くことで、自分らしい働き方ができるのではないか──そう思ったのです。
そのときに思い出したのが、自分自身の経験です。
フリーランスになって強く実感したのは、一人での成長には限界があるということでした。
スキルや経験はあっても、視点や広がりは自分一人分にとどまる。
人と共有することで初めて見えるものがあり、そこで次の成長が生まれる。
だからこそ、「小さな組織を提供する」サービスをつくろうと決めました。
大きな会社のようなしがらみはなく、でもイイ距離感で支え合える小さな組織。
それをかたちにしたのが、workspace coma です。
日々の過ごし方
comaで過ごす時間は、とてもシンプルです。
午前中は専用席で事務作業をまとめたり、プリンターで資料を準備したり。
必要があれば会議室を予約して、クライアントと打ち合わせをする。
フリードリンクで一息つけば、頭がリセットされてまた集中できる。
夕方になれば仕事を切り上げて本を読む人もいるかもしれません。
小さなスペースだからこそ、自分のリズムで過ごせるはずです。
それがcomaの日々の過ごし方です。
ゆっくり育てる
comaは、急いで大きくするつもりはありません。
ここは「小さな組織」を提供する場だからです。
人数が多ければいいわけではない。
少ないからこそ、イイ距離感で支え合える関係が育つ。
それを大事にしたいと思っています。
最初の契約者が女性だったら、そのときに「女性専用にした方がいいですか?」と聞いてみるつもりです。
もし「そうしてほしい」という声があれば、その場から女性限定に変えるかもしれません。
利用者と一緒に、この場所のかたちを考えていきたい。
また、社会保険加入サービスは固定席契約者から始め、そこから紹介制へと広げていく予定です。
信頼できる人のつながりから輪を大切にしたい。
5席だけの小さな拠点。
だからこそ、ひとつひとつの出会いを大切にしながら、ゆっくり育てていきます。
あなたへ
ここまで読んでくださったあなたに伝えたいことがあります。
workspace coma は、大きな施設ではありません。
たった5席だけの小さな拠点です。
でも、その小ささには意味があります。
数を増やすことよりも、一人ひとりとの関わりを大事にしたい。
安心して相談できる距離感を残したい。
そうすることで、自分のペースを守りながら働ける。
そんな関係を育てていけたらと思っています。
もし「ちょっと気になるな」と思ったら、気軽にLINEで声をかけてみてください。
大きな施設ではありません。
5席だけの小さな拠点だから、むしろ気軽に相談してほしいんです。
そして最後に。
私は、誰よりもバランスのとれたバックオフィスとして、あなたの力になれると自信を持っています。
数字も、仕組みも、人との関わりも。
その全部を支えられるのが、私の強みです。